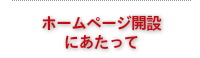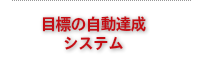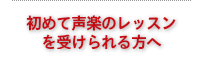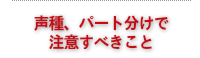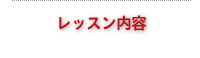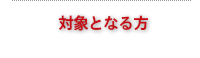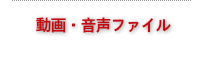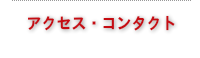良い声の鍵となるイタリアでの体験
メソードについてお話しする前に、私がイタリア留学中に感じたイタリア人の日常生活での話し方の特徴、コンクールやオーディションで知り合った素晴らしい歌手に共通する特徴についてお話し致します。これらの事柄は解釈によっては、既にわかりきった、抽象的な感覚として扱われ易いのですが、良い発声にどう結びついているのか、掘り下げて理解して頂きたい重要な要素です。
1.イタリア人は喋りながら走る方が楽なことを本能的に知っている。
イタリア人が話すことが大好きな国民であることは広く世界に知られています。私の留学していたフェッラーラでは、城壁に沿った素晴らしい景観のジョギングコースがあり、私は運動不足解消の為、イタリア人に混じって毎日のように走っていました。ここで見る光景はイタリア人のお喋り好きを正に象徴しており、日本ではちょっと見かけないような、恰幅の良い子供や主婦、犬を伴った老人等、様々な世代、体型のランナーが、並走する誰かと絶えずお喋りをしながら走っていました。「良かったら一緒に走らないか?」とその場で誘ってくれたベテランと見受けられるイタリア人に、誘われるまま、一緒に走り、お喋りをする中で「話しながら走ると呼吸が乱れて逆に疲れませんか?」と聞いてみたのですが、「呼吸は乱れないし、黙って黙々と走るより、喋りながらの方が疲れないよ!!」と、意にも解さぬ様子で、お喋りを続けました。
なぜ、イタリア人は知らない人を誘ってまで喋りながら走ろうとするのか?
人間は激しい運動をしている間やその直後は呼吸器官を大きく使うようになり、精神的な解放感と共に声のピッチ(甲高さ)が高くなります。逆に考えれば、高いピッチで話せるということは呼吸器官の負の影響を受けにくい状態であり、テンションが上がっている状態を示しているのです。イタリアに長期間滞在し、日本語に接する事が無くなってくると、耳がイタリア語の高いピッチに順応するため、たまたま日本語を耳にしても、口元でモソモソ話しているような不明瞭な言語に聴こえ、それを日本語と認識するのに時間がかかったり、全く気がつかなかったりするようになります。こういった環境下で、たまに日本語を話す機会を得ると、かなりトーンダウンしたテンションの下がった印象を持ってしまうはずです。イタリア人がお喋り好きで、苦も無く、喋りながら走り続けられるのは、この話すピッチの高さが関係しているのです。この話すピッチがイタリア語より低い日本語では、呼吸器官の負の影響が喉に及びやすく、喋りながら走ると、イタリアのように楽にはいきません。我々日本人がベルカントのピッチを習得する際、開放的な気分を心がけ、イタリア語の持っている甲高さを意識する事は非常に重要な要素になってくるのです。
2.言葉のキャッチボールが原則であるが、言い争いになると、お互いが同時にしゃべり続けるような状態が非常に長く続く。
話がもつれ、言い争いで感情が高ぶった時でも、日本人の場合、途中で口を挟むことはあっても、相手が話し終えるのを待ってから主張するといった最低限の言葉のキャッチボールの関係は保たれます。しかし、イタリアの討論番組や町のあちこちで見かける彼らの言い争いは、双方が同時に自己主張をするので、自分の主張していることに対して恥じらいなど全くない、言葉の浴びせかけ状態が非常に長く続きます。
なぜ、そのような状態をすぐに中断することが出来ないのか?
喉の奥の方で話す特性のある日本語は、イタリア語と比べて顔面から頭部への共鳴が少なく、言葉イコール声として認識されるので、自分が発言している時でも、客観的に自分の声を聴き易く、また、話している内容も自己分析し易い状態にあります。一方、頭部共鳴を多く含んだ、顔の前面で話すイタリア語は、言葉イコール響きとして認識される要素が多く、声が頭全体に良く響いているので、自分の声を客観的に聴いたり、自分が話している内容を同時に自己分析することが日本語に比べると難しくなります。2人が同時に話せば、相手の声までも聞き取りにくい状態にし、自分を省みることなく、自己表現する状況を作り易くします。お互いの自己主張の浴びせかけが長時間に渡るのも、こういったイタリア語の持つ言語の特性が一因になっていると言えます。
3.イタリアのテレビ局はイタリアオペラの中継でも視聴者用にイタリア語の字幕を表示している。
自宅でイタリア人の友人とスカラ座で公演されたリゴレット(イタリア人の大作曲家ヴェルディのオペラ)を鑑賞していた時、テレビ画面の下部に歌手の歌に合わせてイタリア語の歌詞が表示されていることに気付きました。
国民には言葉が解るはずのイタリアオペラの放送になぜ、イタリア語の字幕を表示する必要があるのか?
オペラが世界的に広まってきた現在、劇場では初心者でもストーリーが理解出来るように、原語上演の際は歌手の歌に合わせ、舞台の上や横に設置された表示板に翻訳された歌詞が映し出されるようになっています。これは母国語以外のオペラを上演する際の劇場のサービスのひとつです。しかし劇場とテレビという違いはあれ、母国語のオペラに母国語の字幕を表示するのでは辻褄が合いません。その場にいたイタリア人の友人数人に「なぜイタリア語のオペラに字幕が必要なの?」と質問したところ、全員に「当たり前だよ!イタリア人にだって彼らが何を歌っているか聴き取れないんだから」・・・・・・・(^_^;) と一笑に付されてしまいました。 そのオペラが母国語で歌われていたとしても、誰でも歌詞を聴き取れる訳ではなく、ある程度の歌詞を知識として身に付けていた人達だけが知覚できる特別な発音バランスによって歌手の歌声は作られているのです。サロン等の小空間で歌うのであれば、美しい響きと共に子音を含んだ言葉も明瞭に伝えることは出来ますが、オペラ劇場のような広大な空間において声を遠くに飛ばす為には、例え発声に有利な高いピッチのイタリア語であっても話し言葉とは若干異なった発音バランスが必要になるのです。
4.素晴らしい声と観客の心に訴える何かを持っている歌手は発声に関してマニアックな考えではなく、感覚的な理解にとどめている。
世界各国から優秀な参加者が集まる著名な国際コンクールやエージェントの主催するオーディションには非常にレベルの高い歌手の卵達が集結します。私は素晴らしいと思った歌手には積極的に話しかけて、発声について、本番での心構え、日常生活など色々な話を伺いました。特に同じ東洋人でありながら、今や世界中に優秀なオペラ歌手を多数送り出している韓国の歌手からは非常に大きなヒントをたくさん貰いました。その中で『歌の神様に全てを委ねる』 『大切な人を想って歌う』 といった答え方が非常に多かったことに、我々日本人の声楽へのアプローチとは大きく異なっている印象を受けました
なぜ彼らは『神』や『大切な人』といった言葉で歌う事を表現したのか?
無信教を自認する人が多い我々日本人とは異なり、ヨーロッパや韓国では熱心なキリスト教徒が多く、教会などの影響を通じて日常的に神の存在を意識させられています。発声の話を持ちかければ技術論に終始する日本人の声楽に対する考え方はまさに ”心の中の神や、それに相当する絶対的な存在による真の感情より、テクニックや歌詞の解釈といった意図的な事の方が優先される” という声楽の特有な教育環境が影響を与えています。確かに声楽の発声法は正確なテクニックの存在なくしては成り立ちません。しかし、この難しいテクニックでさえも、最終的には『意識せずに行える』レベルにまで導いてゆかなければならないのです。同じ日本人でも声楽以外のジャンルで活躍する歌手の方が表現力豊かに、観客に訴える何らかの力を持っているように感じるのは私だけではないと思います。これらの例から言えることは、心の中にテクニック以外の大きな拠り所となる真の感情を持つことが、彼らの歌を素晴らしいものに感じさせる一つの大きな要因であり、この感情を抜きに歌う事が、必要以上に意識をテクニックに向けさせてしまい、声を喉元から離す事や、音楽を感じ、表現したり、観客の心にダイレクトに何かを伝えることを難しくしてしまう原因になっているのです。
本能的な働きに委ねる必要性
子供が鉄棒や運動器具を使って遊べるような年齢になると、親は「そこをつかんで!ここに力を入れて!」と一生懸命に自分の感覚を子供に伝えようとします。子供は親の言う通りに筋肉に力を入れますが、何か他の力が邪魔をしているようで、なかなか親のイメージ通りに身体は動きません。これは発声においても非常に大事なことで、呼吸法や口の開き方など特定の部位の指摘をしても全体的なバランスにおいては必ず何かが響きを阻害し、良い声で歌うことを妨げてしまいます。
人間には本能的にそれを行う能力と、観察やイメージによってその動きを模倣しながら学ぶことができる能力が備わっています。赤ちゃんが長時間泣き続けても声枯れしない、理想的な発声法を身に付けているのは本能的な能力の為であり、知性が育まれ、話すために声が作り直される過程において、理想的な発声の仕組みは徐々に失われていきます。
歌うという事は極めて原始的な行為で、人類は話すことが出来るようになった時よりずっと前から歌う事を知っていました。言語を話すという進化と共に、発声器官の持つ純粋な歌う為の機能は極度に萎縮しているのです。現在では声楽の手引書が多く出回っており、初心者にとっては声が出る仕組みを学ぶ際に図解された筋肉や部位を確認することによって深い理解が得られるとされています。一方、極めて少ない著名な声楽家の著作においては、実際の肉体の使い方に関しては、ほんのわずかな説明にとどめています。
古いベルカントの発声法に立ち返る必要性
ベルカントと一口でいっても、世界中に様々な流派が存在し、何をもって正当なものとされるのか、これを明確化できないのが日本の声楽の教育現場での悩ましい問題です。しかし、様々な流派があるようでも、大きな区分けの基準は一つしかありません。すなわち”発声器官を直接コントロール出来るようにしようとする近代ベルカント”と”心理的な要素で間接的に発声器官をコントロールする古いベルカント”の違いです。「声は前に?それとも後ろに?」「喉は閉めて歌う?それとも開いて?」「息は腹で支える?それとも背中で?」こういった迷いを初心者に抱かせてしまう大きな原因は、そのベルカントが古いメソードなのか新しいメソードなのかを指導者が生徒に明確に伝えきれていない現実にあります。
古いメソードのベルカントでは、声が完成された時にはこれらの答えは明確に定義することが出来ない、どちらとも捉えられるような感覚に落ち着くはずです。これは人間が言語を覚える前の発声器官の状態、つまり、 ”響き、横隔膜、喉頭などの特別な要素を全く意識していなくても、声枯れすることなく泣き続けられる乳児の発声器官のバランスだから” と言い換えれば分かり易いかもしれません。この文章や図では説明しきれない感覚と論理を理論として解剖学的、生理学的に体系化しようとした瞬間から伝統的な古いベルカントは近代ベルカントへと姿を変えてしまったのです。
科学万能時代の現代において、伝統的な歌唱技術を科学的に解明し、誰もが納得できる形で指導する考えに異論を唱える人は、ほとんど存在しません。現に私自身も知らず知らず、そういった取り組み方に移行していたことは否めません。しかし、完璧な歌手が近代的なベルカントの手法を取る一人の声楽教師から大量生産されることなく、常にごく少数であリ続ける現実が、直接的に発声器官をコントロールする方法の限界を表していると言えないでしょうか?私は本来のベルカント唱法の発声は今後も決して理論として本などでは体系化できないと信じていますし、そうされない事を願っています。
日本人の留学生が必ず指摘される問題点
文化が違えばそこに住む人達の美徳感も全く違います。東洋の中でも、島国として独自の文化を築いてきた我々日本人は歌う為の横隔膜の使い方において、非常に不利な環境にあるといえます。「歯を食いしばる」「踏ん張る」「我慢する」といった我々が美徳とする感情は全て「横隔膜を真下に押し付ける」動きに繋がってしまうからです。この使い方を続ける限り、目指すべき響きは永久にその姿を現してはくれません。誤解しないで頂きたいのは、横隔膜は正しい頭部共鳴が得られていれば既に理想のバランスを伴って自動的に機能しているという事です。この漠然とした横隔膜の働き方が「横隔膜は息を肺に入れるふいごとしての役目を担う」といった機能的なことだけを学んだ人達が勘違いし易い落とし穴であり、本来、睡眠中に誰もが行っている簡単な呼吸法の解釈を難しくしてしまい、ほとんどの日本人が解決できないまま声をダメにしてしまう大きな要因の一つなのです。
イタリア留学中、コンクールの審査員や、レッスンの現場の教師が「あなた方東洋人はなぜそんなに声を押すのか?」と嘆いている場面を私は数多く見てきました。声を押すという表現が一体どこの部位の問題を指摘しているのか?ジュリアーノ先生の指導が無ければ私は永久にこの問題を解決できなかったと思います。「横隔膜が下がる」と「横隔膜を真下に押し付ける」という仕組みの違いを理解することはベルカント習得の上で非常に重要な要素であり、この理解により、声は柔軟性と輝かしさを次第に取り戻していきます。
日本語を母国語として最初に
覚えることが発声を困難にする
東京医科歯科大学の角田忠信教授の著書『日本人の脳』には日本人の右脳と左脳の特別な働きについて書かれています。
人間の左耳から入った音の情報は音楽、機械音、雑音を処理する右脳に行き、右耳から入ると論理的な理解や言語を処理する左脳に行くという交叉状態になっています。この原則は世界中どの国でも共通しているそうです。
しかし、母音、泣き、笑い、嘆き、虫や動物の鳴き声、波、風、雨の音、小川のせせらぎなどは、日本人は言語(子音)と同様に左脳で聴き、西洋人は楽器や雑音と同じように右脳で聴いており、このような特徴は世界でも日本人とポリネシア人だけに見られ、中国人や韓国人も西洋型を示すそうです。
虫の音に母音や音程を感じ、そこに風情、趣を感じ取る我々日本人独特の感性は、右脳に入り易いクラッシック音楽でも、器楽曲は右脳、声楽曲は左脳というように、世界的に見ても特異な反応を示すそうです。面白いのは、日本人でも幼児期に外国語を一番初めの母国語として育てると西洋型となり、外国人でも日本語を一番初めの母国語として育てると日本人型になってしまうということです。
つまり、脳が西洋型か日本型かは人種の違いではなく、育った母国語の違いである可能性が高く、日本人の脳というより日本語を一番初めの母国語として育った脳と言うべきなのです。
この事で解かるように、母音に対する感覚の違いが欧米人と日本人の発声の違いに少なからず関係しているのです。
その他、日本では見逃されている注意点
男性が一番上の5線付近の音で苦しくなるのは、中低音のピッチ、ポジションが間違っているため
男性が苦心する代表的なテクニックとして挙げられるのが5線の上の方のレ・ミ・ファあたりで苦しくなる俗にパッサージョやパッサッジョ(passaggio)、チェンジといわれる音域の回避方法です。指導者により『声をかぶせる(コペルト)』『声を回す(ジラーレ)』『喉を閉める(キューゾ)』といったテクニックが使われます。しかし、この音域で苦しくなること自体が、そこまでに至る中低音の声のポジションが間違っている事を示しており、それを理解するのに私はイタリアで学んでから3年程の月日を要しました。
男声における最も困難な課題が、このパッサッジョの克服であることは間違いありません。古今東西の歌手や音声学者たちの間で「パッサッジョは存在する」「パッサッジョは存在しない」という論争が今日まで繰り広げられています。この問題を考えるにあたって、我々歌手が決して忘れてはならないことは「テクニックは芸術ではなく、観客にテクニックを感じさせた瞬間に純粋な音楽の表現は失われる」という事実です。正しい声のポジションで歌えていれば、観客や録音を聴いた人がパッサッジョの存在の有無については意見が分かれたとしても、その箇所について ”意図的なわざとらしさ” を決して感じないはずです。そして、歌い手自身がこの箇所で ”母音のポジションを確保しつつ、ファルセットの意識を混ぜていく” 以外の特別なテクニックを用いないことは、この『意図的なわざとらしさ』を聴き手に感じさせないための絶対条件となります。
この点について文章や図で説明することは非常に誤解を生み易く、解釈によっては全く違う捉えられ方をされてしまう可能性が有るため、音声ファイルを用意しました。5線の上の方の音域でどのように響きが変化しているのかを良く観察してみて下さい。歌い手の症状によってアドヴァイスする内容や修正する箇所は異なってきますので、実際にレッスンにいらして頂くことをお勧めします。(パッサッジョの概念が存在する理由については『声種、パート分けで注意すべきこと』をご参照下さい)
歌詞を過剰に意識すると発声のバランスは崩れる
ベルカントに最も有利なのはイタリア語を話すイタリア人であることは疑いようのない事実です。しかし、彼らがイタリア語のオペラを歌う時に発音に気をつける必要がないか?と質問されれば答えはNOです。声というより響きを遠くまで届かせる必要のある歌劇場ではイタリア人といえども普段通りの発音の仕方で歌っても客席まで声は届きません。気を付けなければならないことは、言葉に過剰な意識を奪われると、外の響きが半減し、発声のバランスが崩れてしまうということです。裏を返せば、どの国の言葉で歌っても発声方法自体は変わらないという事であり、イタリア語ではうまく歌えるのに、ドイツ語や日本語になると上手く歌えなくなる原因が言葉の過剰な意識によって発声のバランスが変わってしまったことにあることを示しています。歴代の名歌手は教会で子供の頃から歌う機会があり、広大な空間でも言葉を届かせる発音のバランスを自然と身につけました。前にも申し上げた通り、欧米人と日本人の母音に対する感覚は、右脳左脳の使われ方の差が少なからず影響しています。歌詞を漠然と捉えるのではなく、子音と母音の結びつきを事前に検証し、母音の発音を発音しきれない立体的なものにすることによって、母音を頭部の上方に保てるようになり、言語、場所に関係なく歌えるようになります。
喉を開くことの正しい意味を理解しないと、傍鳴りの声になりやすい
喉を大きく開けることは殆どの声楽教師が指摘する共通要素です。『あくび』の形が最も力が抜けて、理想的な形とされていますが、この喉を開ける真の意味を理解するのにもイタリアで相当な月日を要しました。もっとも浸透している指導法のイメージとして”軟口蓋を上げる” が挙げられますが。これを過剰に意識しすぎると声が口の中で増幅され、いわゆる『傍鳴りの声』に陥りやすくなります。「レッスン室で聴くと張りと声量のある声だが、ホールではあまり飛んで来ない」というケースはこの解釈の取違いが大きな原因です。軟口蓋を直接上げようとするのではなく、瞬時に鼻から息が流入する事で ”結果的に上がっていた” 状態になることによって、響きは口の中ではなく、口蓋の上にある頭部空間に自然に増幅していきます。この時に生じる響きはレッスン室では口の中で増幅した響きより、いくぶんピントがずれた感じがしますが、大きなホールでは非常に声量のある、輝かしい張りのある声に聞こえます。
aperto(アペルト:開く)とcoperto(コペルト:覆う)は常に同居している
パッサッジョ付近の音域のテクニックとして認識されており、私自身もイタリアに留学する前は「中低音ではアペルトで出し、パッサッジョ付近に近づくにつれてコペルトし、そこを過ぎるとコペルトしたままアペルトにする」と教わり、その教えを頑なに信じていました。日本では相反するもうひとつの方法として「パッサッジョでは喉をあくびのように更に開いていく」という指導法が存在し、生徒を混乱させる原因になっています。イタリアで何人かのテノールの先生にこの点を質問してみた所、全ての先生が「パッサッジョは存在しない!!」と断言されました。ある先生は「パッサッジョはこういう出し方をするから存在するんだ!」と自ら歌ってその違いを示してくれました。
話すポジションやピッチが日本語より高いイタリア語では、パッサッジョの音域をそれほど意識しなくても比較的楽に高い音に移行できますが、日本語の低いポジションやピッチで歌うと、パッサッジョ音域では特別な出し方をしないと上の音に上がっていけません。そのため、指導者によってはアペルトとコペルトの組み合わせや喉をあくびのように更に開かせることによって克服させているのです。
「パッサッジョは存在しない!!」と断言される指導者に共通しているのは、「低音から高音まで既にコペルト(覆われている)されているが喉は常にアペルト(開いている)」という考え方です。つまり、日本において存在する相反するパッサッジョの克服法は、考えとしてはどちらも間違ってはいないものの、日本語のピッチ、ポジションという枠の中で考えられている方法の為、どちらも不十分であるという事なのです。ちなみに声楽的な意味合いでは、アぺルトは”開きっぱなしの平べったい声”という、悪い声の意味合いがありますが、ここで述べているのはあくまで喉を開くという意味だけに特化しています。またコペルトをchiuso(キューゾ:閉じる)という意味に勘違いされている方が多いのですが、これは間違えです。
頭部共鳴と鼻腔共鳴は全く違う
同じ頭部で響く感覚として混同されやすいのが、この2つの響きの呼称です。教師によっては同一だと解釈している場合もありますが、これも明らかな間違えです。 ”頭部共鳴” というあいまいな呼び方以外に、的を得たふさわしい言葉が見当たらない事が原因と思われます。この違いは鼻をつまんで歌ってみた時に明らかになります。もしそれによって音色が著しく変わってしまうようなら鼻腔共鳴が多く、あまり変わらないようであれば頭部共鳴主導だといえます。鼻腔共鳴が多い発声の場合、風邪や鼻づまりなどの影響を受けやすいのに対し、頭部共鳴主導の発声では歌いすぎ等の場合を除いて、ほとんど一定のコンディションが保たれます。
我々日本人が陥りやすい例を挙げてきましたが、これらの例は枚挙にいとまがありません。というのも声楽を習得するのに本当に必要なことは片手の指の数くらいなのに対し、やってはいけないことは経験を積むに従い、無尽蔵に増えていくからです。このため、レッスンを本業にしたり発声を研究するようになると、より深い理解を得られても、使われている筋肉の状態を過剰に意識してしまう癖が付くようになり、歌うことが困難になるケースが多いのです。先に申しましたように、理想的な発声のモデルは言葉を覚える前の乳児です。つまり、声楽家にとって知識を得ることは必要ですが、歌うということは『どこどこをこうしよう!』という意志がすでに封じ込められていることが前提になり、必要以上に発声の機能について意識することは大変危険な事がお分かり頂けると思います。
ほとんどの声楽家が信じている、発声に対する誤った認識とは?![]()